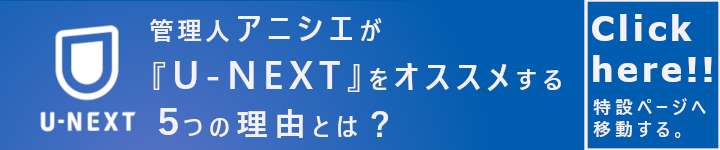評価:★★★★★(95)
| TITLE |
王立宇宙軍 オネアミスの翼 (おうりつうちゅうぐん/オネアミスのつばさ) |
| DATA | 1987年 |
| STORIES | 125分 |
目次
◆あらすじ。
1950年代の地球に似ている『もうひとつの地球』にある『オネアミス王国』。
そのオネアミス王国のには落第軍隊として見下されている王立宇宙軍があった。
水軍のジェット戦闘機乗りに憧れていた主人公シロツグ・ラーダットは、エリートしか入れない水軍への夢を諦めて宇宙軍士官となる。
日々、無難に生きていくことだけで、人生に張り合いを感じられないシロツグは、ある夜同僚たちと訪れた歓楽街で布教活動を行う少女、リイクニ・ノンデライコと出会う。
宗教には無縁のシロツグだったが、彼女に対する下心を秘めてリイクニの住居を訪れ、彼女から『戦争をしない軍隊』である宇宙軍をほめられて思わず発奮し、人類初の有人宇宙飛行計画のパイロットに志願する。最初は呆れていた同僚たちもシロツグのやる気に感化され、宇宙旅行協会の老技術者たちとともにロケット打ち上げの準備を進めることになった。
やがて有人宇宙飛行計画が現実味を帯びはじめると、対立する国家間での陰謀が持ち上がってくる。
さらに多額の税金を使う宇宙開発の是非、開発責任者の事故死などのつらい現実に直面する。そして計画を妨害するため敵国からの暗殺者に命を狙われるという事件すら起きてしまう。
このまま本当に宇宙飛行士となるべきなのか……迷いながらも日々は刻々と過ぎていき打ち上げ当日となる。
敵国との国境近くに設置されたロケット発射台を巡り王国軍と共和国軍の激しい局地戦が始まる。カウントダウンが一旦中止されるも、シロツグは操縦席の中から仲間に打ち上げ続行を呼びかける。
はたして飛び立つことはできるのか。
シロツグを乗せたロケットはカウントダウンを再開する……。
◆普通のアニメ作品として観てはいけない。
最初に断言しておくが、本作は文句なく名作の部類に入るものである。
しかし、だからといって、万人に向けられて作られている作品ではない、ということも付け加えておかなければならない。
この作品を面白いと思えるかどうかは、視聴者側の観るタイミングに大きく関係してくる……と、アニシエは勝手に思っている。
はじめて本作を観たのは中学生くらいの年齢だった。
当時のアニシエのオタク度は、ただのロボットアニメ好きという程度のレベルであった。つまり、幅は狭いし、底も浅い。『オネアミスの翼』という作品が、どういった経緯で、どれくらいのレベルで制作されていったのかなど知る由もないし、また知りたいとも思っていなかった。
だから当然のごとく「ロボットも出ないし、派手なシーンもあまりないし、なんだか地味でつまらないな」という印象しか残らなかった。
そこから10年近く、この作品の評価はそのまま『地味だけど名作らしいよ』という世間の評判と同じような評価のまま時が過ぎていくことになる。
だが、この過ぎていく時間というのが、実はこの作品を心底味わうためには必須の要素であったことを、後に知ることになる。
◆旬な見頃は25歳を過ぎてから。
『オネアミスの翼』という作品は言うなれば、
有人宇宙ロケット開発ドキュメンタリーをアニメーションで(つまりフィクションという形をとって)表現しようとして作られた映画である。
なのでその演出的な技巧においてもアニメ的な定石というよりは実写フィルム映画のようなテイストを感じさせる雰囲気がある。
ヒロインであるリイクニ・ノンデライコのキャラクターデザイン(=見た目)や設定なども、決して完全無欠の美少女という描き方はせず、人間的な欠陥をどこかに抱えたまま生きている素朴で敬虔な少女として描かれている。
また、地球によく似た環境ではあるが、明らかに異世界である世界設定に関しても、特に懇切丁寧に誰かが説明してくれるわけではない。キャラクターたちの会話から得られる漠然とした情報から、各々が推察していくしかない。昨今の異世界ファンタジーものによくあるような、世界や歴史を紐解いてくれるような親切キャラは存在しない。
この、視聴者をある意味で置いてけぼりのままで進む物語の作り方と、序盤における主人公シロツグ・ラーダットとその仲間たちの怠惰で諦観に満ちた人生観は、そのまま現実社会を鏡映しているかのようである。
特に確固たる目的を持って就職したわけではない職場。自分たちとは無関係に動き続ける社会。世界の成り立ちなど知らなくても人生は続いていくし、たとえ世界について何も知らないまま人生が終わってしまったとしても、それを残念だとも思わない。
社会という現実の中へ、ある日を境にしてとつぜん放り出された新社会人としての若者というものは、多かれ少なかれ、こういった人生初の軽い挫折感というか、徒労感を味わう瞬間がある。
それは、おそらく世界が自分たちに対して、親や学校が教えてくれたように優しく、親切で、平和を大切にする世界とは程遠かったということを肌で感じるからであろう。
そういった不親切な現実を、世界背景を説明しないことで視聴者に疑似体験させることにより、そこに住む若者たちも同じように世界について知ろうとしなくても生きていけるという、感覚を理解することになる。
そう考えれば、実社会での生活だって、これに似ているということに気づくだろう。
アニシエにしたって、何も常日頃から世界情勢に気を配っているわけではないし、ある国の政治情勢が不安定だからといって、その国の成り立ちから国民性を調べ上げて、なぜいま不安定なのか? などという考察をするわけでもない。
よその国の戦争は対岸の火事よりもさらに関心の薄いトピックスでしかない。
それよりも目の前の仕事や育児に目を向けざる得ないし、じっさいそれで過不足なく生きてもいける。
本作はリアリティの点で高い評価を受けることが多いのだが、その評価の大部分が映像の緻密な描写に偏る傾向がある。
しかし、本作でもっともリアルな部分というのは、じつは登場人物たちの精神的な変化(あるいは成長)にあるとアニシエは思っている。
だからこそ、大人になって幾度となく視聴しても心に響くのである。
というわけで勝手に本作の見頃を考えてみる。
まあ、なんとなくではあるが25歳前後というのが一般的にほどよい視聴のタイミングではないだろうか。
ひとつのロケットを開発する、それに人を乗っけて打ち上げる。
言葉で書けば一行で済んでしまうこの行為に、はたしてどれだけの時間と予算と人材が必要なのか?
それを肌身で実感できるのが、おそらく25~30歳くらいだろう。
規模の大小は立場や職種によって差異があるにせよ、だいたい社会に出てある程度の責任が生じてくれば、自分を取り巻くプロジェクトの周囲には、かなり色々な人達が関わり合っていることに気づくはずである。
その中にあって、うまくいくこともあれば、失敗することもある。自分の意志とは無関係に、やたらと評価されることがあったりするかと思えば、なんの心当たりもない面で嫌われたり怒られたりすることもある。
そんな社会の悲喜こもごもを若い感性で受け止められる年代というのが、上記の年齢幅だと考えられる。
じっさい、アニシエが大人になってドハマリしたのは26歳くらいのことである。
まあ話せば長くなるし、たいして面白いエピソードでもないので割愛するが、仕事とプライベートにおいて自分の本当にやりたいこととは、なんなのだろう? というよくある精神的葛藤に悶々としていた頃に本作をたまたま観たのだ。
中学生時代に観た、退屈な作品というイメージは払拭され、そのヒューマンドラマのリアリズムと緻密な映像によって描き出される美しさに、我知らず感動したことを覚えている。
偶然とはいえ、観るタイミングが完全に自分の境遇と(ある部分で密接に)重なり合っていたからこそ、ここまで強烈に記憶に残り、それ以来、機会があるごとにリピートしているのであろう。
アニメに限ったことではないけど、あるひとつの作品と出会うタイミングというのは、けっこう大事なファクターのひとつだと思っている。そして、その作品が本当に自分にとって必要なものであれば、(それが何度目の視聴かは関係なく)かなりの高確率で、絶妙なタイミングでもって作品と再開する機会がある、というのが持論である。
◆英雄とはなんなのか? を問う作品。
主人公シロツグは、自身の夢が叶うものではないということを知り、日々の生活に理想を求めることをしなくなった若者として登場する。
彼が宇宙飛行士を目指すキッカケは、ものすごく単純であり、もっと言えば不純な動機でもある。
ヒロインであるリイクニの気を引きたいから。
これが最初の出発点である。
無人のロケットですら何度も失敗している宇宙軍にあって、ほとんど自殺行為と言ってもいい決断なのだが、当のシロツグはそれほど事が重大だとは思っていない。
宇宙飛行士に立候補した直後の心境としては、まだ怠惰な生活の延長線上にあり、訓練が必要以上にきつかったり、じっさいに命の危機に直面したら逃げればいい、くらいの感覚でしかなかったのであろう。
要はリイクニの心を掴むための、ある種のスタイルとして宇宙飛行士という肩書が欲しかっただけである。
しかし、じっさいに訓練や勉強を真面目に行ううちに、シロツグの心境も刻々と変化していくことになる。
彼女に好かれるため、という目的からやがて、仲間の真剣な支援を感じ、さらにロケット開発に情熱を燃やす博士たちと知り合う。
有人宇宙飛行計画が現実味を帯びはじめるにしたがって、その波紋は社会現象にまで発展する。
気がついたときには、シロツグ本人ですら自覚のないままにオネアミス王国の英雄とまで言われるようになってしまっていた。
その一方で、多額の予算を必要とするロケット開発などやめて、その予算を社会福祉に回せという抗議団体が現れる。
シロツグ本人が欲しかったのは、あくまでスタイルとしての宇宙飛行士であって、貧困にあえぐ社会を踏み台にしてまで手に入れたい栄誉なんてものではなかった。あまつさえ敵対国からの暗殺者に命を狙われるまでになっていた。
嫌になったらいつでも辞められる。
それくらい単純に考えていた当初の環境とは、すでにあらゆる部分で違っていた。
このまま本当に続けるべきなのか?
迷い、悩むシロツグは、自分の出発点であるリイクニの元へ訪れる。
彼女との関係もまた、刻一刻と変化していくわけだが、時が経てば互いの生活も変わるし、見方も変わる。
ただなんとなく漠然と可愛いと感じていた彼女の、その慎ましい生活というものは、じつは逃れようのない貧困の中で生きている社会の縮図そのものだという現実であることを垣間見たとき、シロツグは恋心と憐憫(れんびん)と歪んだ欲望が入り交じる、自身でも説明のつかないような感情を抱え込むことになる。
恋をした相手の、見たくはない生活の一部を見てしまった瞬間の、なんとも言えない気まずさ。
そんなシーンを描くアニメーション映画は、後にも先にも本作くらいであろう。
どうせ描くならば、普通はもっとショッキングな出来事や場面にするはずである。
しかし『オネアミスの翼』では、あえてそこを劇的なシーンとはせず、あくまで生活の一部という見せ方をすることによって、そこにリアルな人物像を作り出すことに成功している。
リアルな人物像とは、そこに迷いがあり、選択の過ちがあり、そして大きな変化などはなにもない、という当たり前の現実感が感じられることである。
普通のアニメーションであれば、瞬間的な出来事や刹那的な言葉ひとつで、劇的に心境を変化させて(目が輝いたりして)いっきに解決へと突き進むことがままあるが、本作ではそのようなシンプルな答えは何一つ提示しない。
しかし、非常にスタティックな展開でありながらも、これら一連のシーンは、何度見返しても胸が苦しくなるような青年の心の有り様をリアルに描いている。
さらに、どうにも抑えきれない衝動に突き動かされて、シロツグがリイクニを襲う場面がある。
これは結局未遂に終わるのだが、敬虔な殉教者としての思考を持つリイクニは、そのことで彼を咎めることすらせず、むしろ自分が彼の頭に燭台をぶつけたことを謝罪する。
呆気にとられるシロツグであったが、そのことで自分を取り戻すきっかけを得る。
どれだけ周りが英雄視しようが、自分は愚かであり、そしてその間違った選択は、世界はおろかひとりの少女の心さえ変えられないほど小さいものでしかない。
それは救いでもあり、振り出しに戻ることができる間違った道であったことに気づく。
いよいよロケット発射場へと向かう前日、再びリイクニの元を訪れるシロツグ。
だが、彼女は出掛けていて、そこには彼女が引き取り育てている少女のマナしかいなかった。
無口で無愛想なマナにもすっかり慣れてしまったシロツグは彼女に伝言をお願いする。
シロツグが無事に帰還したとき、マナにおみやげを買ってきてあげると言い、彼女になにが欲しいか尋ねると、マナは「おほしさま」と言う。
そのリクエストに頭を悩ませるシロツグは、彼の真似をして同じような顔をしてみせるマナの姿をみて、思わず笑みがこぼれていた。
無愛想で、何事にも無関心な少女だと思っていた存在が、じつは自分をよく観察し、それを真似る意味。
シロツグの間違った選択では、何も変えることができなかった。しかし、自分が決意したことによる行動は、ほんの些細なことであるが確実に人を(小さな少女ひとりであったとしても)変えていく可能性がある。
それを気づかせてくれたマナという少女の存在は、これから打ち上げに命を掛けるに充分な理由となった。
英雄とは、決意を持って立ち上がる人間のことである。
この瞬間にこそ、ほんとうの意味でシロツグは英雄になることを決断したのだ。
◆異色のキャスティング。
物語とキャラクターについてのドラマツルギーにおいてリアリズムを求めている作品だということはすでに述べた。
そして、そのリアルな質感を描くためにアニメとしてもっとも重要な要素のひとつは言うまでもなく声優である。
文字通り、その作品の世界観における息遣いを感じさせてくれるのが、それぞれのキャラクターを演じる声優陣であるといえる。
主人公であるシロツグ・ラーダットを演じたのは、ナレーションで有名な森本レオ氏。
その名前だけ見ると「え? 青年役がレオ?」と誰もが首を捻るようなキャスティングである。
じっさい、未だにあのキャスティングはミスマッチだという人もいるのだけれど、アニシエ的には繰り返し観るたびに、じわじわとシロツグの声として、これ以上のハマリ役はいない、という確信が芽生えてくる。
オープニングのモノローグにしても、やはりあのアンニュイで、どことなく気が抜けたような寂しさが漂う声質でなければ、青年の惰性で生きている脱力感は表現しきれないのではないだろうか。
終始、物腰柔らかい口調であるシロツグが、クライマックスで大声を張り上げるシーンがある。
最後の最後で吐き出される、その思いの丈が詰まった言葉の圧力に、ぐっと胸が熱くなる場面である。
普段物静かな声優としてのイメージのある森本レオさんだからこそ、緩急に富んだこの名場面で視聴者をはっとさせるほどのインパクトを与えることができるのだ。
そこまで考え抜かれてのキャスティングだとしたら(たぶんそうだろう)、これは見事な配役である。
グノォム博士を演じた故・大塚周夫氏をはじめ、主人公を取り巻く周囲の声優陣もそれぞれの役柄によく合っていて、違和感を感じることなく作品に没頭できる。こと声優に関しては、非の打ち所がないほど考え抜かれていると言っていいだろう。
他に面白いキャスティングとしては、劇中のテレビアナウンサー役で徳光和夫を特別出演していたり、当時人気のあった外国人タレントであるアントン・ウィッキーとオスマン・サンコンが端役のコメディアン役で出ていたりする。
さらに細かいことを言うと、最後のエンドロールでオスマン・サンコンのテロップが『オースマン・サンコン』となっている。綴りの発音としては、もしかしたらこちらの方がより近いのかもしれないが、当時の茶の間からしてすでに『オスマン』として定着していた感はある。
しかし、外国人であっても(日本語の中で可能な限りという意味で)ちゃんとした発音通りの名前を載せようというスタッフ側の真摯な態度が伺える、ちょっとしたいい話でもあります。
どちらが真の発音に近いのかはわかりませんけどね(笑)。
◆GAINAX(ガイナックス)はココからはじまった。
ガイナックスとは、そもそもアマチュア映像集団である『DAICON FILM(ダイコン・フィルム)』が母体となっている。
もはやアニメ好きで名前を知らない人はいないと言っても過言ではない山賀博之・庵野秀明・前田真宏・貞本義行らが参加していた団体で、当時彼らはまだ学生であった。
本作で映画監督デビューを果たした山賀博之は当時24歳。またスタッフも総じて若く、アマチュア出身ならではの熱気とこだわりを持って制作に取り組み、結果他に類を見ないような高水準のアニメーション映画が作られることになった。
アニシエが個人的に最も鳥肌が立ったシーンは、打ち上げまでの残りカウント20秒からの秒読みである。
よくある演出手法で言えば、この秒読みというシーンは、カットを稼いだり削ったり、さんざんギリギリまで引っ張って緊張感を高めるような方法が多いのだが、本作ではカウントの20秒間をいっさい引き伸ばさないで打ち上げまでを描く。
こうして文字で書いてみると「それって当たり前じゃないの?」と思われる人もいるだろう。
だが、このカウント・シーンをちゃんとその秒数内で描くアニメというのは、あまり存在しない。
細かいことではあるが、こうしたよくあるシーンであっても手を抜かずに描き出すからこそ、リアリティを大事にしている作品であると言えるのだ。
◆リイクニの布教・シロツグの神秘体験。
今回見直して、改めて深読みして楽しんだのが、ヒロインの立ち位置である。
なぜ、リイクニ・ノンデライコは外国輸入系だと思われる布教活動を行い、その経典をシロツグが読むことになったのか。
このくだりは、物語に直接関わってくるような話ではない。
しかし、人は(その人がどれだけ無信心論者であれ)少なからずの神秘体験を人生の中で得るものである。
人が集団的コミュニティで生きていくということは、そこでは必ずなにがしかの信仰対象が存在する。
宗教に限ったことではないけれど(山や海そのものが信仰対象となる地域もある)、それを象徴的に描くということは、実はシロツグが宇宙へ到達したさいに感じる神秘体験への大きな布石となっている、ということを今回の視聴で気付かされた。
「どのような形でも構いません。祈りを捧げてください」
多神教、唯一神、無宗教、なんでもいいのだ。祈りは形ではないのだから。
シロツグが得た神秘体験は、リイクニの敬虔さをも超越することとなる。
現実の宇宙飛行士の中でも、その神秘体験から宗教家へと転身したケースがあり、製作者は(ロケットマニアの岡田斗司夫がいるのだから、これは明らかに意図的である)それをモデルとして、この物語の結末を描いたのではないだろうか。
一方でSF映画であるスタンリー・キューブリック監督作品『2001年宇宙の旅』へのオマージュとしての性質も兼ね備えていることは双方を視聴したことがある人ならば誰しもが気づくところだろう。
なぜ(本物の)宇宙飛行士が神秘体験を得るのか? という、その疑問から、それを必然として描くために、リイクニの布教という素材があるのではないか、などと勝手な深読みをして楽しむ。
そんな余地がまだ残されているほど、アチコチに奥深さが備わっている作品だと言える。
◆総評。
すぐれた文学作品や映画は、10代・20代・30代と、その作品に出会う時期によって感じ方が変わる。
これと同じような体験ができるアニメというのは、そう多くはない。
かなり久しぶりの視聴ではあったが、いつ観ても色褪せない作品というのは存在するものだと実感する。
映像の質感やデザインなどに時代が感じられたとして、それは作品の本質とはなんら関係がない。でなけば、現代において名だたる作家たちの著作・映像作品など残せていないことになってしまうからだ。
本作を一言で表すならば
『青年群像劇に必要なすべての要素が盛り込まれている作品』
だと断言できる。
ここまで丁寧に描かれているひとりの人間の成長劇を、長編アニメではなく2時間弱の作品できっちりと過不足なく作られている、というのが何より凄いことだ。
そして、それを作ったスタッフのほとんどが20代であり、商業作品をきちんと作り上げるノウハウもないままに完成させたというのは、もはや伝説的な凄さではないだろうか。
映像自体がまったく古く感じられないのは(もちろん世代もあるだろうけど)、それだけ緻密な世界設定を徹底して構成している証拠でもある。
オネアミスの文明レベルは、日本で言うなれば昭和30年くらいだと推察される(※ガガーリンが世界初の有人宇宙飛行を成功させたくらいの年代)。
そこにはテクノロジーに対する期待が込められた時代特有の活気が存在する。
自分たちの生活に、新しいツールが入りつつあり、ライフスタイルが変革されようとしている過渡期の高揚した社会的な熱気。そういった世界観そのものの空気が伝わってくる作品というのは、100作品中に1作品あるかないか、くらいの確率だろう。
本当に製作されるのかどうか疑わしいが、続編の『蒼きウル』を死ぬまでに観たいものである。
最後に。
坂本龍一氏が作曲したテーマ曲は、一度聞いたら耳から離れないほど素晴らしい楽曲である。
インストゥルメンタルな曲で、ここまで耳に残る音楽を想像しうる坂本氏の音楽的感性とは、やはり本物であり、赤字覚悟で彼を起用した若きガイナックスのスタッフ陣に拍手を送りたい。
最後に観てほしいパイロット版。
本作のブルーレイソフトを購入すると、映像特典として本編が公開される前に制作されたパイロット版を観ることができる。
シロツグやリイクニのデザインが違えども、そのクオリティは本編に引けをとらない。
というか、本編を作る前にここまで完成されているものがあるということが、スタッフの狂気にも似た執念を感じさせる。
アニメを産業として捉えることなく、作りたいものを作る、という若手クリエーターたちの本気の遊びが、本作を実現させた大きな原動力であったことが伝わってくる。
そろばんを弾きながら作品をつくる大人の感覚では、ここまで徹底した作り込みはできなかったであろう。
誰もが「素人が映画なんて作れるわけがない」と批判的だったなかで、ここまでのことを成し遂げた人たちが、その後にNHKでアニメを作ったり(ナディア)、社会現象にまで膨れ上がった作品(エヴァンゲリオン)を作り上げていくことになるとは、誰が想像し得ただろうか。
ちなみに『オネアミスの翼』はあくまでサブタイトルである。
メインタイトルは(スタッフの強く硬い信念の元)『王立宇宙軍』であることを末尾にお伝えしておこう。
アニメをたくさん観たい! そんなアナタにオススメの動画配信サービスとは?
記事内関連商品のご案内
王立宇宙軍オネアミスの翼/4Kリマスター版
◆色褪せない映像美を4Kで!
2001年宇宙の旅/Blue-ray版
◆SFの祖。オネアミスの翼をより深く味わうための1本です。